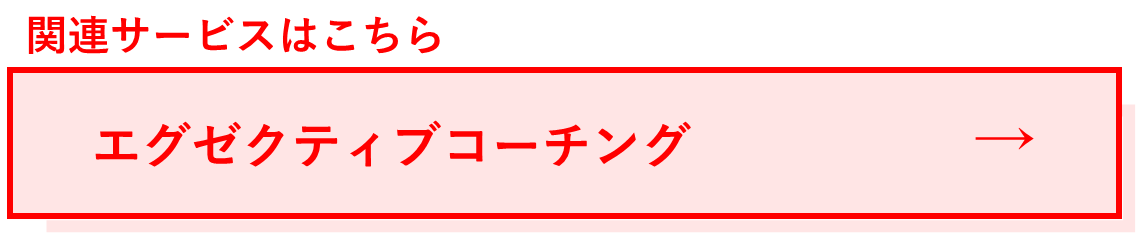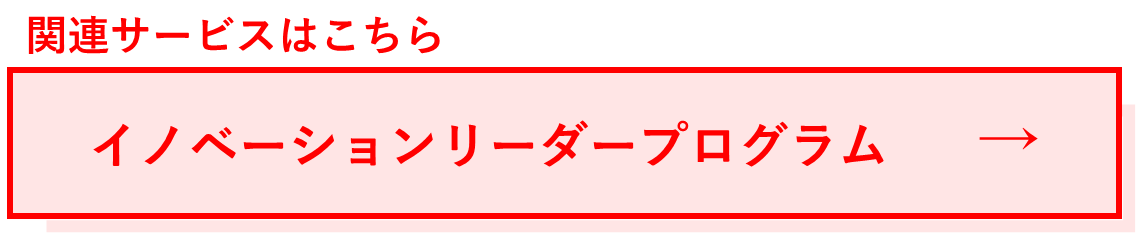- エグゼクティブコーチング
- イノベーションリーダープログラム
株式会社 MonotaRO
お客様に聞く(エグゼクティブコーチング、社内研修)ー 株式会社MonotaROー
【MonotaRO様】成長に不可欠な社員のベクトル合わせにコーチングを導入

成長に不可欠な社員のベクトル合わせにコーチングを導入
クライアント企業情報
株式会社 MonotaRO

https://www.monotaro.com/
2000年10月設立。事業者向け工場用間接資材の販売している企業です。
工具や手袋など「間接資材」1000万点以上のネット販売で急成長する
MonotaRO(モノタロウ)。『日経ビジネス』が2016年1月11月号で
独自調査により発表した成長率ランキングでは、日本企業でトップでした
(全体では9位、調査対象は北米、欧州、アジア、日本の代表的な上場企業)。
今後も成長し続けるには、社員相互のコミュニケーションを深め、社員のベクトルを合わせるための仕組みづくりが不可欠だと、同社は考えています。その仕組みづくりに向けた、エグゼクティブコーチングなどの導入効果や今後への期待などについて、代表執行役社長の鈴木雅哉氏にうかがいました。
ご担当者様
代表執行役社長 鈴木 雅哉 氏
1975 年生まれ。98 年、立教大学社会学部社会学科を卒業、住友商事に入社。2000 年、住商グレンジャー(現 MonotaRO)出向、会社設立に携わる。06 年 3 月、住友商事新素材・特殊鋼貿易部。同年 5 月、楽天入社。07 年、MonotaRO マーケティング部長。12 年 3 月より現職。
お客様の課題・ご要望
- ・経営幹部陣のマネジメント経験の少なさ
- ・部下とのコミュニケーションの改善
ビジネスコーチの提案・サポート
- ・上級管理職向けエグゼクティブコーチング
- ・イノベーション・ワークショップ
- ・「破壊的質問力」習得するための研修トレーニング
「互いに敬意を持ち仕事すること」で成長し続ける
Q:今後も成長し続けるために、社員相互のコミュニケーションを重視されていますね。
A:それは、創業当初からの理念でもあります。創業者である会長の瀬戸欣哉による「創業の志」にも「互いに敬意を持ち仕事すること」を掲げています。
当社では、仕入れ、出荷などの物流、システム開発など、様々な仕事があります。お互いの仕事を知るための研修を行ったり、可能な限りローテーションしたりするようにもしています。
また、ビジネスモデルなども少しずつ変えながら成長しています。そうした中でも常に、お客様にとって何が大事か、仕事において何が大事か、自ら判断し、行動することを、社員に求めています。そのためにも、会社が目指していること、考えていることを理解し、社員間で共有し合えるような場づくりを重視しています。社内研修なども、そうした場づくりを目的に行っています。
Q:「創業の志」には、人を大切にすることが成長につながるという考え方が表れていますね。
A:人を大切にするというのは会社の基本方針です。
2000年に住友商事からの出向者5人で設立した当社は、わたしが社長を引き継いだ12年には120人ほどに増え、現在ではその倍の260人ほどにまでなり、年間30~40人ほどのペースで増えています。一方で、離職率は年間1~2%程度と少ない。これらも、人を大切にしてきた結果であり、社員の仕事への満足度の高さの表れでもあると思います。
ただし、会社にとっての一番の財産は「仕組み」だと考えています。「ビジネスモデル」といってもいいでしょう。会社は仕組みで成り立っている。
その仕組みの中で、どのような働き方が求められるのか、どのようにしたら成果を出せるのか、それらのために必要なものは何か。社員には、そうしたことを教育していくというのが、基本的な考え方です。
経験不足を補い若さのメリットを生かす
Q:経営幹部向けには、エグゼクティブコーチングを導入されていますね。
A:当社の経営幹部は、わたしと同年代の40歳前後の人がほとんどです。それまでにマネジメントをほとんど経験してこなかった人もいます。
若さゆえに、過去の慣習などにとらわれることなく、必要な変革をスムーズに進めやすく、会社の成長にプラスになるというメリットもあります。一般的な大手企業のように、ほとんどの幹部が55歳以上であれば、同じようにいかないのではないでしょうか。
半面、幹部として、どう考え、どう行動すればよいか、悩むことも多い。やはり、経験がものをいう部分もあります。経験不足を補うという面で、コーチングはとても有効だと思います。それによって、若さのメリットも、より生かせるようになります。
Q:どのようなきっかけで、コーチングの導入を具体的に考え始めたのでしょうか?
A:一つは、グループ長たちの悩みですね。当社には中間管理職に相当するグループ長が30人ほどいます。彼らも含め全社員から毎週200数十通の週報が上がってくるのですが、その中で「部下とのどのようなコミュニケーションを意識すればいいかわからない」という悩みが多かった。毎週10分でも15分でもいいので、各部下と1対1で面談するというルールがあるのですが、そこでどう接すればよいのか、どうすればコミュニケーションの質が良くなるのか、みんな悩んでいました。
部下との接し方、コミュニケーションの仕方を身につける手段として、コーチングのようなものが必要だと考えるようになったわけです。
もう一つは、わたし自身のことです。
現在でもそうですが、わたしにとって最も優れたメンターであり、師匠ともいえるのは、創業者の瀬戸だと思っています。ただ、こういう社長というポジションについて、第三者的な立場の人からの意見にも興味を持つようになりました。社長になると、まわりが気を遣うようになり、気をつけなければ、自分が「裸の王様」になってしまいかねません。そう感じたからでもあります。
そして、社長のわたし自身もそうですし、幹部らやグループ長らもそうですが、どう考え、どう行動するか、そのモデルのようなものがあってもいいのではないかと考えるようになり、コーチングの導入を検討し始めたのです。
自分の考えを整理しながら「気づき」が得られる
Q: いろいろなコーチングプログラムの中から、ビジネスコーチのプログラムを選んだ理由を、お教えください。 A:まずは、自分がコーチングを受けてみることにしました。コーチングで知られる会社数社から提案いただき、それぞれのコーチングを受けてみました。
A:まずは、自分がコーチングを受けてみることにしました。コーチングで知られる会社数社から提案いただき、それぞれのコーチングを受けてみました。
その中で、どうしても自分には合わないというコーチもいました。例えば、「キャリア」「バリュー」というような言葉を使って、「あなたはこんな経営者を目指すべきだ」というように導いていこうとするタイプのコーチです。どちらかというと、ティーチングに近いですね。わたしの求めているのは、こういうコーチではないのだと強く感じました。
当時、わたしは社長になって4年くらいで、これから続けていくに当たり、仕事のバランスや優先順位などをうまく整理できていないように感じていました。それを整理し、判断していく上での気づきが得られるようなコーチングを必要としていたわけです。そのことに合致したのが、ビジネスコーチであり、コーチの橋場さんだったということだと思います。コーチのパーソナリティによる部分も大きい気がします。コーチングではありますが、ほどよくティーチングの要素があるのもよいと思います。
継続する仕組みやサポートの充実を
Q:実際にコーチングを導入されての効果などは、いかがでしょう?
A:幹部へのコーチングは、特にマネジメントの経験が浅い人にとっては、大きな効果があったと感じています。「質問力」のトレーニングなど、具体的なプログラムを通して、マネジメントとしての目標、課題、意識などについて整理でき、考えや行動に生かせていると思います。
「質問力」に関しては、グループ長にもセミナー式の研修を受けさせています。総じて社内では好評で、それぞれに実践しているようです。
Q:さらに今後、どのようなプログラムを期待されますか?
A:コーチングや研修で身につけたことを、継続して実践していくことが重要です。ただ、実際には難しいこともある。それは個々人の問題かもしれませんが、継続するための仕組みづくりも必要だと思います。そうした仕組みづくりへのサポートや、何か本当に困った時のサポートなどがあるとよいかもしれません。
社員が個々に力があることと、会社として成果が上がることは全く別のことです。会社の成長は、会社の仕組みそのものにかかっています。社員一人ひとりが、会社のビジネスモデル全体のどこをどう担っているのかを理解し、社員のベクトルを合わせていくことが、会社の成長には必要です。
会社が成長し続けるために、コーチングなどを活用して、こうした人材育成を継続して進めていきたいと考えています。
*参考情報:「ビジネスコーチに依頼した業務の詳細」
上級管理職向けエグゼクティブコーチング
| 項目 | 内 容 | 備 考 |
| 形式 | 個別エグゼクティブコーチング | コーチングの事前・事後にヒアリング(多面評価)も実施 |
| 受講者 | 9名 | 社長1名、執行役(部門長)6名、グループ長2名 |
| コーチング期間 | 1名あたり8か月 | 2ヶ月に3回*8か月(計12回) |
イノベーション・ワークショップ
| 項目 | 内 容 | 備 考 |
| 形式 | ワークショップ形式 | ビジネスモデルキャンバス等を用いて自社のビジネスモデルの再構築のための演習を実施 |
| 受講者 | 24名 | 社長1名、執行役(部門長)6名、グループ長17名 |
| コーチング期間 |
1日8時間×2回 |
上級管理職はオフサイトにて実施 |
「破壊的質問力」習得するための研修トレーニング
| 項目 | 内 容 | 備 考 |
| 形式 | 集合研修(ワークショップ形式) | 質問力に関する基礎理論および演習を中心に実施 |
| 受講者 | 44名 | 社長1名、執行役(部門長)6名、グループ長37名 |
| コーチング期間 | 1日8時間×3回(3クラス) | ※2016年10月以降に研修後のフォローアップ(クラウド活用、フォロー研修)を実施予定 |