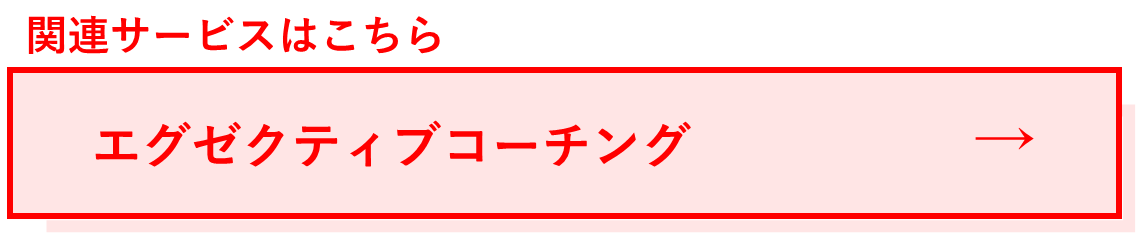- エグゼクティブコーチング
パーソルホールディングス株式会社
(エグゼクティブコーチング)
経験豊富なコーチから気づきを得て次世代リーダーが自走。パーソルHDが取り組む「エグゼクティブコーチング」の意義とは

パーソルホールディングス株式会社
グループ人事本部 人事企画部 部長 山崎 涼子 氏
企業を取り巻く環境変化が激しい中、サクセッション・プランの策定や次世代リーダーの育成がより重要視されるようになってきています。パーソルホールディングスでは、それぞれに異なる課題を抱える次世代リーダー層の支援を目的として、2019年よりエグゼクティブコーチングを導入しました。一律の研修プログラムでは得がたいコーチングの成果や意義を、人事企画部 部長の山崎 涼子 氏に伺います。
クライアント企業情報
パーソルホールディングス株式会社

労働者派遣事業・有料職業紹介事業等の事業を行うグループ会社の経営計画・管理並びにそれに付帯する業務を担う。
グループ会社数:計134社(国内37社、海外97社/2023年6月1日時点)
連結従業員数:6万7274名(2023年3月31日時点)
ご担当者様
グループ人事本部 人事企画部 部長 山崎 涼子氏
2008年にインテリジェンス(現パーソルキャリア)に新卒入社。
入社から現在まで、採用・人材開発・人事システム・人事企画等、人事領域を一貫して担当。現在はタレントマネジメントやエンゲージメント向上のための仕組み構築を担う人事企画部の責任者に従事し、パーソルグループ全体の人事戦略を推進。
お客様の課題・ご要望
異なる課題を抱える、次世代経営リーダー候補(管理職)の支援・
ビジネスコーチの提案・サポート
エグゼクティブコーチング
次世代リーダー育成には、Howを伝える場ではなく「内省の場」が必要
——エグゼクティブコーチングを導入した背景をお聞かせください。

当社はグループ共通の人材開発ポリシーを掲げ、次世代経営リーダー候補となる管理職の育成に力を入れています。そのための手法のひとつとしてエグゼクティブコーチングを導入しました。
エグゼクティブコーチングを選んだのは、管理職層の抱える課題が個別に異なるためです。研修などで具体的な“How”を一律に伝えていくプログラムよりも、それぞれのテーマに応じて、リーダーとして自らのあり方や生き方を内省してもらう場が必要ではないかと考えていました。
——エグゼクティブコーチングの導入にあたり、対象者はどのように選定したのでしょうか。
当初は育成支援を中心目的として、各ビジネスユニットのトップ(事業会社の社長に相当)から対象者を選抜してもらっていました。各ユニットから1名ずつ、全体で5名が参加する形です。
2023年からは経営トップ層のグループ横断異動施策と接続し、組織をまたぐような大きな変化を伴う異動をした人を対象として、コーチングを希望する人にプログラムを受けてもらうことにしました。それまで慣れ親しんだ環境から新たな環境へ移り、組織にうまく適応しつつ成果を出していかなければならない。そんなプレッシャーを抱える層への支援を強化するため、エグゼクティブコーチングを活用しています。
——指名方式から手挙げ方式へ大きく転換されたのですね。
以前は上長から対象者へ選抜理由や期待感を伝えてもらい、コーチングのテーマ設定や振り返りには上長や人事も加わっていました。これはこれでひとつの成功パターンでしたが、2023年からは組織の大きな目的に合わせて、またコーチングの成果をより高めていく意味でも、「本人の意思」をより重視するようにしました。

現在はプログラム開始前のタイミングで私が対象者全員と会い、コーチングは自分自身と向き合う上で有効な場であること、異動後のタイミングだからこそコーチングの機会を生かしてほしいことなどを伝え、対象者が今どのような状態にあるのかを聞いています。その上で、本人が望めばコーチングに参加できるようにしているので、高い目的意識を持って取り組んでもらえるのではないかと考えています。
上長との会話にはない「コーチから得られる気づき」の意義
——プログラム全体の進め方についてお聞かせください。
1年間に合計8回のコーチングセッションを実施しています。当社は4月から新たな期が始まるため、最初の四半期を過ぎ、新組織での仕事が落ち着きつつある7月に第1回を開催。その後は概ね月1回のペースでセッションを進め、年度末を迎える前に完結できるようにしました。
テーマ設定は千差万別ですが、対象者と「テクニカルなことを教わる場ではない」ことを確認し合っていますね。初めてコーチングを受ける人は、経営に役立つHow toを教えてもらえる場だと誤解しがちです。もちろん組織長を担う人にとって、足元の目標達成は非常に重要ではありますが、それを解決することにコーチングを利用すると人材力の育成につながりません。事前のオリエンテーションでもこの点を理解してもらい、それぞれの価値観やありたい姿を内省してもらいながら、第1回のセッションでテーマ設定のすり合わせを行っています。

——エグゼクティブコーチングの実施を通じて、どのような手応えや変化を感じていますか。
自分自身が大切にしている価値観や人生観などを認識し、アップデートした自己概念をもとにビジョン構築していく重要性を語ってくれる参加者が多いですね。こうした場を貴重な機会として捉えてもらっています。
レイヤーが上がれば上がるほど周囲から指摘を受ける機会が減り、自らで気づきを得ることは難しくなるもの。一方、プログラム参加者は一度気づきを得られれば、独自のスキルや過去の経験を生かし、自走しながら問題を解決していける力を持っています。だからこそ、気づきの種をもらえるコーチングの場が有益に作用しているのでしょう。
——コーチからの「問い」だから、得られる気づきがあるんですね。
私自身も部下を持つ立場として日々さまざまな問いかけを行っていますが、上司はどうしても自分の経験の延長線上でマネジメントしがちであり、過去の経験則以上の問いかけはなかなか難しいもの。だからこそプロフェッショナルであるビジネスコーチの力を借りる意義を感じます。コーチングの技術はもちろんのこと、ご自身の経営経験などを踏まえてさまざまな角度から問いかけてくれるコーチの存在は本当に大きいですね。
経営戦略や企業文化についても「阿吽の呼吸」で会話できるコーチ陣
——次世代リーダー育成に関して、今後予定している施策があればお聞かせください。

グループ経営の推進をテーマにして、今後も組織横断で次世代リーダー層の異動を進めていくことになります。その支援策として、今後もエグゼクティブコーチングを最大限に活用できるようにしたいですね。
また、さらに次の世代であるリーダー候補層を育てていく観点では、タフアサインメントの実施も検討しているところです。若手・中堅から重要ポジションへの抜てきを進め、責任のある経験を積み重ねられるようにして、リーダーに求められる力を伸ばしていければと考えています。
——今後、ビジネスコーチとしてもさらなる提案を続けていきたいと思います。現在までのビジネスコーチのサポートを、どのように評価していますか。
まず、コーチ陣の層の厚みが他社とはまったく違うと感じます。エグゼクティブコーチングの参加者はさまざまな課題を持ち、新組織へ着任したばかりで「抜擢されたものの、役割への期待に応えたい思いと現実の課題とのはざまで葛藤する」と悩んでいるケースもあります。そんな状況でも、コーチの皆さんはさまざまなバックグラウンドをもとに、本人が最大限に高いパフォーマンスを発揮できるよう寄り添ってくれています。
長く取り組みを一緒に進めてきたこともあって、コーチの皆さんが当社を深く理解してくれていることも心強いですね。経営戦略や企業文化についても、阿吽の呼吸で会話できる一心同体感があります。
これはビジネスコーチの関係者の皆さんも同様です。当社を長く担当する中で深い理解をしてくれて、当社の経営層に対する支援施策において、私たちが気づいていない視点でのアドバイスももらっています。私たちはこれからも大きな変化を続けていくと思うので、今後も高い視点で提案してほしいと考えています。