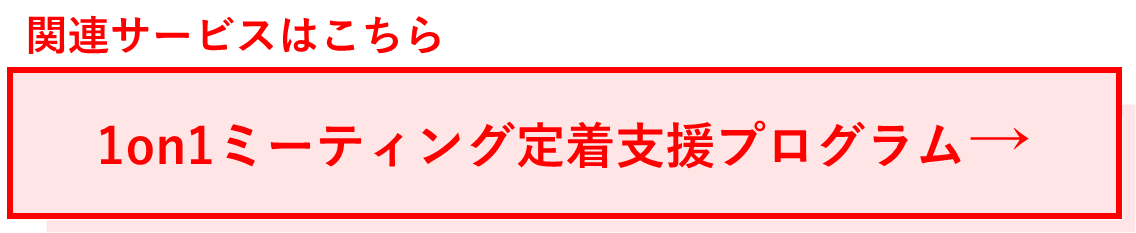- 1on1ミーティング定着支援プログラム
ビッグローブ株式会社
お客様に聞く(1on1ミーティング導入プログラム) ービッグローブ株式会社 ー
スキルを身につければ実践できる。1on1を定着させるために、「真面目な風土」を生かす

自社の風土を生かした1on1
クライアント企業情報
ビッグローブ株式会社
インターネット等のネットワークを利用した情報サービスの提供および、これに付帯または関連する一切の業務を運営。
従業員数約500名。
ご担当者様
杉森 隆行 氏:
エンジニアとして20年以上にわたり開発部門に在籍した後、2017年に人事部門へ異動。現在は人事部長として全社の風土改革を推進
する。
中川 亮 氏:
新卒で組織人事系コンサルティングファームに入社。IT関連サービスを手がける大手事業会社の人事を務めた後、2019年にビッグローブ株式会社に入社。
お客様の課題・ご要望
- 長年にわたり築き上げられてきた企業文化の変革
- 新しい挑戦をする風土の醸成
- トップダウンの風土や、上意下達のコミュニケーションスタイルからの脱却
ビジネスコーチの提案・サポート
- 手挙げ制での1on1研修
BIGLOBEの組織課題:社会インフラを支える「真面目な風土」がある一方で、新たな挑戦は少なかった
――1on1導入前に、貴社ではどのような課題があったのでしょうか。

杉森氏:当社はNECの事業部門からスタートし、主力の回線事業をベースに成長してきました。回線事業は安定的な収益があるものの、人口減少社会にあっては成長の限界も見えてきています。
私が人事部門に来た2018年、経営層からは「イノベーションを生み出し、次世代の基幹事業を育てなければならない」というメッセージが出されていました。ただ、改めて社内に目を向けてみると、新しい挑戦をする風土が醸成されていないと感じていました。
中川氏: 私は2019年に中途入社してから、思いのほかトップダウンの風土があることに驚きました。縦のラインが明確で、業務における確認手順なども細かく、きっちりと定められています。社会のインフラを支える企業としては必要なコミュニケーションスタイルですし、それを否定するわけではないのですが、イノベーションを起こすにはちょっと物足りないようにも感じました。
――「トラブルやミスを未然に防ぐ」という意識が強いからこそ、上意下達のコミュニケーションスタイルが定着していたと。
杉森氏:言われたことを全うする「真面目な風土」が根付いているのは良いことです。反面、指示されていないことを自律的に取り組もうとする動きはあまり見られませんでした。これは、イノベーションが求められる開発部門の技術系メンバーも同様です。
1on1導入のきっかけ:「1on1をやるべき」というトップメッセージで、重要タスクだと認識してもらう
――1on1導入のきっかけを教えてください。
杉森氏:私が人事部門に来てから、個人的にビジネスコーチのセミナーに参加したことがきっかけでした。
私は開発部門にいた頃、部下と1on1を独自に行っていたんです。そのため、当時開発部門にいた部下は、1on1の重要性を理解してくれていました。とはいえ彼らが昇級してマネージャーとなってからは、「やる意味は分かるけれど忙しくて……」という状態で、開発部門内に1on1がなかなか浸透していきませんでした。ただ意義を伝えるだけでは進まないのだと実感していましたね。
――どのようにして1on1の機運を高めていったのでしょうか?
杉森氏:セミナーに参加して「トップに動いてもらうことが重要」だと知りました。そこで中川とともに作戦を練り、各部門のトップである本部長と副本部長へ働きかけていくことにしました。

中川氏:当社は大きく分け5つの本部で構成されています。
各本部長へは、パルスサーベイの結果をエビデンスとして1on1の必要性を伝えていきました。パルスサーベイは本部長に提案する根拠として効果的だったと思います。感覚的にではなく、毎月の数字をもとにして「上司と部下の関係不良」といった現状を示すことができたからです。本部長の理解を得た上で、2020年6月より、各本部においてキックオフを当社独自に実施しました。
――まずは貴社独自で1on1を導入されたんですね。
はい、当初は内製で1on1を推進し始めました。本部長からは「なぜ1on1をやるのか」を語ってもらい、さらに杉森から1on1の重要性を伝えていきました。まずは私たちが最も働きかけやすいコーポレート本部でキックオフから研修、日々の実践まで一気に進めて、その知見をもとに他の本部へ広げていきました。
――導入においては、あえてトップダウンで進めることでスピード感や確実性をもたらしているのですね。
杉森氏:日頃から忙しい管理職層は、「時間があったらやってね」というメッセージではなかなか動いてくれません。「1on1をやるべきである」というトップメッセージによって、重要タスクだと認識してもらえるようにしました。ある意味では、当社の真面目な風土を逆手に取った策と言えるかもしれません。

中川氏:同時に、取り組み開始のハードルを下げることも強く意識していました。1on1の推奨頻度は「2週間に1回、30分」。かつ、部下との関係性によって、頻度や実施時間は柔軟に対応してほしいと伝えています。信頼関係を築いている部下となら月に1回でもいいかもしれません。一方で中途入社したばかりの社員には、毎日10分ずつなどコミュニケーションの頻度を高めることが必要でしょう。このようにして「ちょっとずつでもいいからやりましょう」というメッセージを伝えていきました。
ビジネスコーチのサービス導入理由:1on1を「受ける側」の視点を持つことで得た気づき
――管理職向け研修を貴社独自で実施する中で、苦労した点はありましたか?
中川氏:2020年、コーポレート部門を皮切りにスタートして以降、部長・グループリーダー・マネージャークラスをメインターゲットとして、約70名に研修を実施してきました。
管理職層に1on1の意義が伝わってからは、それを否定する人はいませんでした。一方で、具体的な方法についての知見はほとんどありませんでした。たとえば「1on1の途中で相手が沈黙した場合はどうすればいいのか」など、スキル面でつまずいてしまう人が多かったんです。逆に言えば「スキルさえ身につければ実践できる」ということ。
――ここまでのプログラムを内製で企画し、1on1導入に否定的な人がいない状態にできたのは、貴社の風土や社員の特徴を上手く捉えて推進した結果だと感じました。
中川氏:各本部長を筆頭に、管理職層が協力的になってくれたおかげで、導入が上手く進んだように思います。しかし、このタイミングで、1on1を内製で運営する限界を感じて、ビジネスコーチにスキル研修の依頼をすることにしました。2021年4月からの研修では、誰でも応用できるスキルを学んでもらうことに注力しています。
杉森氏:私もビジネスコーチの研修を受講したひとりですが、研修で学んだフレームワークはとても使いやすいと感じました。営業におけるトークスクリプトのように、「どんなふうに質問するか」「返ってきた答えに対してどのように応じるか」といったことを段階的に学び、現場で応用できる実感を得ました。
また、ビジネスコーチの研修では管理職同士で1on1のロープレを行い、ここでも大きな気付きがありました。「1on1で質問されても受ける側はすぐには答えられない」という、やってみて初めて分かることがあったんです。
――1on1を実施する側の視点だけでなく、「受ける側」の視点を持つことも重要なのですね。
中川氏:研修後には参加者から「今後は研修以外の場でも、管理職同士で1on1ができる場を用意してくれませんか?」という提案も寄せられました。受ける側の視点を知ることで、1on1の意義をより深く感じてもらえたのだと思います。
――ここまでの取り組みを通じて、どのような変化を感じていますか?
中川氏:パルスサーベイの結果でいうと、さまざまな項目の中でも特に低かった「挑戦する風土」のスコアが2020年に比べて上がっています。以前は全社平均で100点中60点、他社の平均スコアと比べても低い状況だったのですが、直近ではこれが65点となりました。上司と部下のコミュニケーションが変化したことによって、「挑戦していいんだ」という空気が少しずつ生まれてきているのではないかと見ています。

杉森氏:管理職の中には、1on1の機会があることで「部下と話すための良いきっかけになる」と感じてくれている人が多いです。
昨今はハラスメント防止対策が進んでいる中で、上司は部下とのコミュニケーションの機会をつかむのが難しくなっている面がありました。一昔前のように「ちょっと飲みに行こうか」と簡単に声をかけづらく感じる上司が多いようで、コロナ禍においてはなおさらです。
「部下と話す時間をどうやって取ればいいんだろう」と悩んでいる上司も少なくない。その意味では、「1on1で30分話す」という機会があることは上司にとって大きな意味を持っているんですよね。
「質よりも量」のフェーズを過ぎて向き合う「1on1とビジネスの接続」
――今後の人材開発における展望や構想をお聞かせください。
中川氏:直近では、1on1の効果測定や満足度調査などを行って、進捗度を可視化する予定です。その結果を踏まえてさらなる打ち手を考えたいですね。1on1を行うことが当たり前の組織となるために、管理職層の行動原理を変える必要があります。ここからどのように行動を変えていくかが、1on1の定着には重要だと認識しています。
杉森氏:BIGLOBEには、良い人材がたくさんいます。みんな真面目だし、人がいい。これまでは良い関係性でチームワークを発揮してきましたが、この強みをさらにビジネスに生かしていければ、会社としてもっと成長できるはず。そのためにキーとなるのがマネジメントです。上司と部下のコミュニケーションをさらに活性化させ、人の良さを引き出せる組織にしていきたいです。

中川氏:「やると決まればどんどん前に進んでいける」のは、私たちの大きな強みですよね。今後、イノベーションを生み出していく組織になるためには、自分たちでゴールを決め、自分たちで動かしていく力が求められます。1on1文化を通じて、社員のイノベーティブなアイデアをどんどん引き出していきたいですね。
――1on1の取り組みは、今後どのように進化させていくのでしょうか?
杉森氏:当初は「質よりもコミュニケーションの量」を重視して導入しました。その意味では、期待していた以上にコミュニケーションは活性化し、管理職層もメンバー層も1on1の場を活用してくれています。
注意したいのは、「1on1は会社を成長させるための手段」ということ。今後は、ビジネスの成果につなげるために、1on1の質も追いかけていきます。部下の悩みを聞いて「そうだね」と共感しているだけでは物足りないんです。その次のステップを、ビジネスコーチのサポートを受けながら今後の研修の中で創っていきたいですね。
中川氏:「1on1は1on1」「ビジネスはビジネス」といったように、今はフレームが分かれてしまっている面があるのかもしれません。導入フェーズを過ぎた今は、1on1とビジネスをつなげ、本来の目的であるイノベーション創出に向けて活用していくべきタイミングなのだと捉えています。
「挑戦する風土」の醸成のために、今年は「人事が言うから取り組む」のではなく、「自分たちにとってなぜ1on1が必要なのか」をみんなで議論し、考えていく組織にしたいです。

その他弊社サービスの詳細については、ページ上部の「サービス」タブより各項目を選択のうえご確認ください。
個別のご相談をご希望の方は、下記お問い合わせフォームもぜひご活用ください。