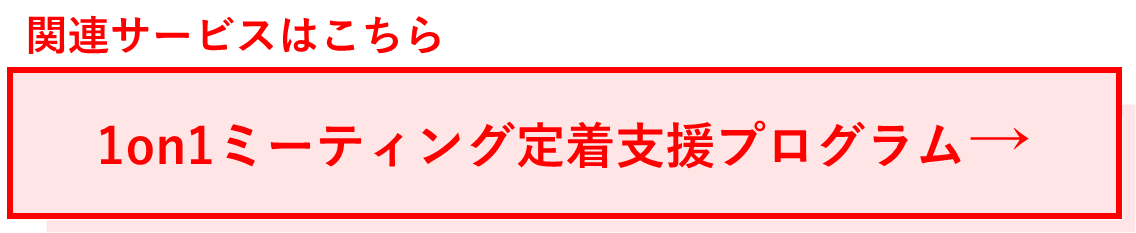- 1on1ミーティング定着支援プログラム
パナソニック株式会社
(1on1)
事業・マネジメント変革に向け1on1を導入しました

パナソニックではビジネスコーチに1on1の導入支援を依頼しました
クライアント企業情報
パナソニック株式会社
経営の神様とも呼ばれる松下幸之助氏が始めた旧松下電器より今に至るまで歴史を作りつづけている日本が誇る電機メーカー。一般家庭向けの家電からエレクトロニクス分野まで様々な電機製品を開発、生産している。
連結売上高7兆9822億円、従業員数27万4143名。(2018年3月31日現在)
ご担当者様
大橋 智加氏(パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社 常務 人事・総務担当)
お客様の課題・ご要望
-
1on1 導入成功の秘訣について
ビジネスコーチの提案・サポート
-
HR カンファレンス 2018ー秋ー講演会
ビジネスコーチ 橋場氏:なぜ、1on1は事業・マネジメント変革に有効なのか
ビジネスコーチは、ビジネスコーチングのメソッドを軸に人材育成や組織開発を行い、これまでに500社以上を支援。近年、1on1はコーチングの中でも欠かせないスキルとなっており、この2、3年は同社への問い合わせも増えているという。1on1とは上司と部下が1対1で定期的に行う対話だ。橋場氏は1on1を次のように語る。
「1on1とよく比較されるのは年次評価制度です。これは年に2、3回、上司から部下に対して評価を伝えるものです。1on1はこれとは異なり、上司が部下の考えていることを引き出しながら、成長支援を行います。通常は1on1の中でコーチング、ティーチング、フィードバックなどを効果的に組み合わせて行われます」
橋場氏は「1on1は事業・マネジメント変革に有効」と語る。そのメカニズムはこうだ。組織の生産性向上には、職場の「心理的安全性」を高める必要がある。その職場の「心理的安全性」の確保には1on1ミーティングの実施が有効。そして「心理的安全性」が確保されると「良質な問い」が生まれ、事業・マネジメント変革が促される。
「心理的安全性は最近よく使われる言葉で、Google社のプロジェクトで有名になりました。同社が4年以上をかけて、どんなチームがパフォーマンスを出しているかを調べたところ、共通していたのが心理的安全性の高さでした。チームメンバーが『安心して働ける』『本音が言える』といったことを感じていると、高いパフォーマンスが出せるのです」
事業・マネジメント変革にはイノベーションが必要になるが、すべての新しい新規事業は「問い」から始まる。「問い」が生まれるには、何でも話せる場が必要。そのため、心理的安全性の確保に役立つ1on1ミーティングが求められるのだ。
では、心理的安全性がある職場とは何か。橋場氏は例として「そのチームの中で安心して働ける職場」「そのチームの中で本音を言い合える職場」「上司に対しても率直な意見を言える職場」「チームメンバーからあなた自身が本当に必要とされていることを実感できる職場」「仕事をしていてワクワク感がある職場」をあげる。
「1on1トレーニング時に、『心理的安全性のある職場について、御社は100点中何点ですか』と聞くと、上司より部下のほうが点数は低くなります。この差をどうやって埋めていくかと考えることが改革につながります」
パナソニック 大橋氏:パナソニックの事業・マネジメント変革に向けた1on1導入と現状
続いて大橋氏が登壇。パナソニックは社内に四つの事業カンパニーを設けている。大橋氏が所属するのは、BtoBソリューションを担うコネクティッドソリューションズ社(CNS社)。大橋氏が今回1on1導入に踏み切った目的は、事業・マネジメント変革の基礎となる風土改革だった。
「現在はビジネスモデルが見えにくい時代です。そのため、特に我々が転換を目指すBtoBソリューション事業においては、多様な顧客に対する深い思考が必要になります。そのためには、個々のレベルで答えが決まっていない課題について考え、解決を図らなければいけない。このことをより深く理解し、考えるためには、顧客や自組織以外の様々な人たちとの時間や接点を増やす必要があります。しかし、近年は家電中心のプロダクトアウトの風土が、知らず知らずのうちに部下が上司を気遣う態度につながってしまい、内向き仕事や形式的な仕事が増えていました。この『知らず知らずのうちに』というところが問題でした」
大橋氏は人事として、自由に発言してもよい雰囲気、誰かの発言によって可能性を見出そうとするスタンスを、社内に確保したいと考えた。その解決策が1on1ミーティングだったのだ。
「風土改革をしようとトップも発信していましたが、なかなか変わらない。私はこの固定化した雰囲気を変えるために、現場の上司と部下の関係に変化が必要と考えていました。そんなときに1on1が評判になっていると聞き、この施策に飛びつきました。加えて、上司の変革に対する貢献を評価したいとの思いから360度評価もセットで導入することにしたのです」
2017年秋に社内に1on1の導入の意志を伝え、2~3ヵ月間検討。トップからも導入の必要性を語ってもらい、2018年4月には導入が決まる。期間半年ほどのスピード決定だ。1on1ミーティングの導入の位置付けは、現場の上司と部下のコミュニケーションを進化させること。目的は、上司発の面談から部下主体の対話に変え、仕事の成果の最大化、個人の自律的な行動・成長を促す。そして、部下を主体とした1対1の対話を通じ、気付きを与えて、自律的な行動を引き出していく。
「頻度のガイドラインは2週間に1度。時間は最低15分。部下が7人いれば2週間に約2時間必要になります。勤務時間は2週間でおよそ80時間ですから、その2%を使っていただきたいとお願いしました。必ず1対1で面談を行い、話の主体は部下本人。上司は傾聴いただくことが基本です。そして人事も現場と一体運営を行うということで、課題を吸い上げ解決する体制を構築しました」
導入セミナー・研修および体制構築では、ビジネスコーチの力を借りている。外部に依頼した理由は二つある。
「一つ目は、1on1は初めてなので専門家の知見をお借りしたかったこと。二つ目は、1on1が一般に広く行われていると理解していただきたかったから。現場の組織責任者には1on1の大切さについて腹落ちいただく必要があったので、外部の方に講師をお願いし、一般的に行われているものと理解していただくようにしました」
1on1の導入研修は、全国の拠点で係長以上全員が受講した。これまでに、63回約1800人に対し研修を行っている。受講者アンケートでは「大変に役立つ84%」「役に立つ15%」と、過去にないほどに大変高い評価が得られたという。また、人事では上司用のハンドブックと部下用のパンフレットを作成。上司用のハンドブックでは主旨だけでなく、気を付けること、具体的な話の仕方、部下との接し方など細部を説明する内容とした。また、Q&Aでは現場からの質問を吸い上げて内容を共有した。
「1on1の施行が一通り終わったところで社員の皆さんにアンケートに答えていただきました。『上司との1on1に満足していますか』では『とても満足+満足している』で75%。『話しやすい雰囲気ですか』も肯定が8割以上と、1on1開始時にしてはよい数字となっています。ただし『仕事の成果の最大化につながっていますか』という質問では、肯定が半数程度でしたので、これからよりよいものにしたいと思います」
ディスカッション:1on1導入を成功させる方策とは
ここからは吉田氏の司会で、ディスカッションが行われた。
吉田:まず、一つ目のテーマです。1on1導入に至るまでの苦労や、導入時に工夫したことや経緯について、お聞かせください。
大橋:2017年の夏ごろに「1on1と360度評価をセットで導入したい」と部下に伝えたところ、皆一様に反対でした。理由は長時間労働の削減の障害になるからです。それでも「結果として効率化につながる」と訴え続けました。社長の樋口にも伝えると、別の会社での経験から、やや不安な様子でした。しかし私は「今現場レベルでの対策を施さないと何も変わらない」と思い、時間を短時間化することで社長に了承をもらいました。経営会議にかけると役員からも「現場のコミュニケーションは足らない、当然やるべき」と激励があり、無事1on1の導入が決まったのです。
吉田:1on1を導入して、「事業・マネジメント変革」という観点での最大の成果とは何でしょうか。また、今後のさらなる成果につなげるうえで重要だと思うことは何ですか。

大橋:成果は、上司と部下の関係を変えることが徐々にできてきていることです。様々な場面での社員アンケートの結果を見ても、受け身から能動的になり、気持ちも前向きに変わっています。まだ導入して日は浅いですが、現場の変化を感じています。
橋場:私は大橋さんが風土改革のために導入された点が重要だと思っています。1on1を行ったからといって、すぐに劇的なイノベーションが起こるわけではありません。しかし、職場に心理的安全性を生む土壌に変わる点に意味があるのです。では、どうすればイノベーションが起こせるのか。ポイントは二つあります。一つ目は、質問や問いが投げかけられるようになり、社員がいろんなことを考えるようになること。どんな事業も小さな問いから始まります。能動的に社員が課題を考えるようにならないと、そういった問いは生まれません。二つ目は、ビジネスモデルといった高いレベルで変革しようと考えるようになれること。特定のすぐれたプロダクトを作れば勝てる時代はもう終わっています。これからはビジネスモデルを優れたものにしないと勝てない。そのための議論は1on1の風土がなければ生まれません。
吉田:これから1on1を導入される皆さんに対するアドバイスをお願いします。
大橋:アドバイスは二つあります。一つ目は自社の事業にとって非常に大事な施策だと腹落ちいただくことです。「社員間のコミュニケーションをよくするため」と発信すれば、そのこと自体、誰も反対しません。しかし、目的はそうではなく、経営課題を解決するために是が非でも必要な施策と理解していただくこと。そのレベルにどれだけ落とし込めるか。二つ目は、とにかくやってみるところまでは持っていくことです。反対する人もいる。実行までも時間がかかる。それでも「とにかく一度はやってみる。やってみてから文句を言おう」という風土に、なんとしてでも変えていこうという思いを持つことです。私の場合は、ビジネスコーチさんに導入セミナーをお願いして協力してもらいました。
橋場:「やってみよう」というスタンスだったから、短期間で実施までこぎつけたのだと思います。世の中でも企業施策では「ひとまず動こう」という考え方が強くなっています。実際、そんな会社はとてもスピーディーに価値を提供できている。こういった考え方は、人事領域でも当てはまると思います。
ここで会場の参加者から「1on1を始めても上司ばかりが話してしまう。どうすれば変えられますか」という質問があった。
橋場:1on1はそもそも上司自身が「何のためにやるか」を理解していただかないと、ミーティングもうまくいきません。私たちはパナソニックさんでも上司の皆さんに対して2時間半の導入セミナーを開きました。そこで伝えたのは三点。一つ目は、1on1がなぜ必要か、どういう意味があるのかを伝えること。二つ目は、実際の1on1ミーティングを見ていただくことです。部下が8~9割を話すミーティングとはどんなものか。その場でデモンストレーションを行いました。時間にして10分程度ですが、通常とは違う点を見てもらうと説得力が増します。三つ目は、長時間労働の削減に役立つことを理解していただくこと。新たに時間をかけてでもやるべき価値があると腹落ちしていただくため、事例などを交えて説明しました。この3点セットを2時間半で体感してもらうと、かなりの人が賛成してくれます。最初から賛成派が多数にはなりにくいでしょうから、しっかりとご説明する時間をつくっておくべきだと思います。